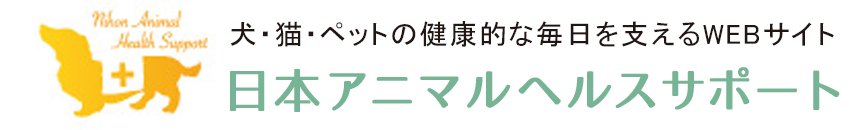現在、飼い犬の半数近くが肥満傾向または肥満と言われています。
今回は、犬が肥満になりやすい原因や太らないようにする食事の工夫。ダイエットする時に大切なポイントについて説明します。
- 目次 -
犬が肥満になりやすい原因
犬の祖先であるオオカミが群れで生活していた時代に、食事の順番は群れのリーダーから先に食べ、リーダー以外は競争で食べていました。
その名残で犬は「食べられる時に食べられるだけ」食べようします。
犬が一日に必要とするカロリーは、成人の男女と比べるとわずかこれだけです。
1日のカロリー必要量
- 成人男子 2500kcal
- 成人女子 2000kcal
- 30kgの犬 1400kcal
- 10kgの犬 600kcal
- 5kgの犬 350kcal
- 2kgの犬 180kcal
人と比べると犬は思った以上に小さく、1日の必要カロリー量も少ないのです。
犬は自分では食事の量をコントロールできず、飼い主さんが与えた分だけ食べてしまいます。量や回数をきちんと管理してあげないと、食べ過ぎて肥満に繋がります。
犬の適正体重の考え方
犬の適正体重は1歳の頃の体重が目安です。
大型の品種を除けば、1歳くらいでほぼ大人になります。
この時期の体重がその個体の標準体重に近いとされています。1歳の時の体重の記録や写真がある場合は、現在の体重や体型を比べてみると、現在の状態が良くわかります。
犬では適正体重の15%以上を超えると「肥満(太り過ぎ)」といわれています。例えば、10kgが適正体重の犬が11.5kgを超えると「肥満」、「たった1.5kg」、と感じてしまいがちですが、体重の少ない犬にとっては、大きな違いなのです。
犬の体重管理は「何kg増えた(太った)、または減った(痩せた)」と考えるよりも「何%増えた(太った)、または減った(痩せた)」と考えることが大切です。
太らないように!食事の工夫
人間の食べ物を与えることはやめる
まず、人間の食べ物を与えている場合はすぐにやめましょう。人間の食べ物には塩分や脂分が多く含まれているので、犬の健康にもよくありません。
フードの量を減らす
市販のフードの裏側に記載されている体重別・犬種別の適正量はあくまで目安です。今与えている量では多いかもしれないと思ったら、かかりつけの獣医さんと相談してフードを少しだけ減らしてみましょう。
おやつにも工夫をする
フードは問題ないはずなのに太っていく場合、ほとんどはおやつの与えすぎが原因です。急に与えるのをやめるのではなく、小さく切って複数回与えるなどして、少しずつ量を減らしていきましょう。また、ささみや茹でた野菜など、低カロリーの物に変えるのもいいでしょう。
減量(ダイエット)用の食事療法食について
食事の工夫をしても体重が増えてしまっている場合は、低カロリーでも必要な栄養素がすべてとれるよう、特別に調整された減量(ダイエット)用の療法食をおすすめします。
重要なのは、体の「余分な脂肪」だけを減らして「健康的に」減量することです。
通常のフードを減らすだけでは、筋肉や内臓や骨を維持するためのタンパク質やビタミン・ミネラルなどが不足しがちになります。
減量用の療法食は、フードのかさを減らさず、満腹感を保つようにする、などの工夫がされていて、必要な栄養素を減らさずにカロリーを抑えることができるように作られています。
ただし、急にフードを変えてしまうと、犬が食べなかったりお腹をこわしたりする場合があります。今までのフードに少しずつ混ぜていく形で、徐々に移行してみましょう。
犬のダイエットに大切な4つのポイント
今は「肥満」だけが問題となっている犬でも、「高血糖」「高脂血」「免疫力低下」が表面化するリスクが潜んでいます。そのため、犬のダイエットでは、これらの全てにおいて、対策をとることがポイントとなります。
1.低糖質
糖質・炭水化物を少なくしましょう。
特に、消化吸収されやすいブドウ糖や砂糖、可消化性デンプンといった糖質・炭水化物に注意が必要です。これらを多く含むドッグフードは避けるようにしましょう。
「甘いもの」はもちろん、炊飯した白米も吸収されやすいため、量は控えましょう。
2.低脂肪
「低脂肪」「脂肪の質」に気を配り、脂肪の量を少なくしましょう。
脂身の多い肉よりも鶏のササミや胸肉、魚など、脂肪分の少ないタンパク源を、加熱は軽く茹でる程度にとどめて与えましょう。(高温により、脂肪の酸化が進むため。)
3.タンパク質・アミノ酸・ビタミン・ミネラルの補給
タンパク質はしっかりと与えましょう。犬の活力が維持され、基礎代謝を高めることにもつながります。さらに、タンパク質の構成要素「アミノ酸」もチェックしましょう。特に「リジン」「カルニチン」という2種のアミノ酸が、犬の脂肪燃焼・ダイエットに効果的です。
更に、ビタミンC・ビタミンE・セレン・ナトリウム・カリウムの適した配合バランスが、犬のダイエットに貢献します。
4.免疫力キープ
犬のダイエットに特徴的なポイントが「免疫力の維持」です。免疫力キープが、犬の健康につながることはもちろん、基礎代謝を高め、ダイエットにも関係してきます。
腸内環境、特に小腸を健康に保つことが重要です。小腸には、免疫細胞の60%以上が集まっているとされています。善玉菌を増やすこと、腸に負担をかけない食事を与えること、などを心がけましょう。
まとめ
犬は自分ので食事のコントロールが出来ません。
ついつい食事やおやつを与え過ぎることで肥満を招いてしまいます。
肥満は人間と同様、様々な病気へのリスクがあります。
食事管理と適度な運動で適正体重を保ち、愛犬が健康で長生きできるように気を配ってあげましょう。